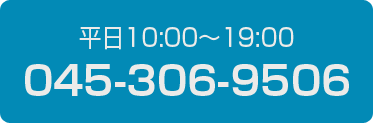社用車とは何か?定義と基本的な役割
社用車とは、企業が業務を遂行するために利用する車両の総称を指します。営業活動や顧客訪問、配送、社員の送迎など、用途は多岐にわたります。
重要なのは、社用車には 購入して所有する車(社有車)だけでなく、リース車やカーシェア車両も含まれる という点です。つまり、「所有」に限定されない「業務利用のための車」を総じて社用車と呼ぶのです。
社用車と営業車の違い
営業車は、特に顧客訪問や営業活動に使う車を指します。社用車の中に営業車は含まれますが、社用車には配送用車や役員車もあるため、営業車=社用車ではありません。
社用車とマイカー使用の違い
一部企業では、社員が自家用車を業務に利用する「マイカー通勤・営業」を認めています。しかしこの場合、ガソリン代や保険の取り扱い、事故時の責任範囲が複雑になります。社用車を導入すれば、リスク管理や費用処理が明確になり、社員の安心感も高まります。
社用車と社有車の違い
混同されやすい用語が「社用車」と「社有車」です。
社用車:会社の業務で使う車全般(リース・レンタル含む)
社有車:会社が購入し、資産として所有する車
例えば、リース契約で導入した車は「社用車」には該当しますが「社有車」ではありません。会計処理や管理コストを考えるうえで、この違いを理解しておくことは非常に重要です。
社用車について
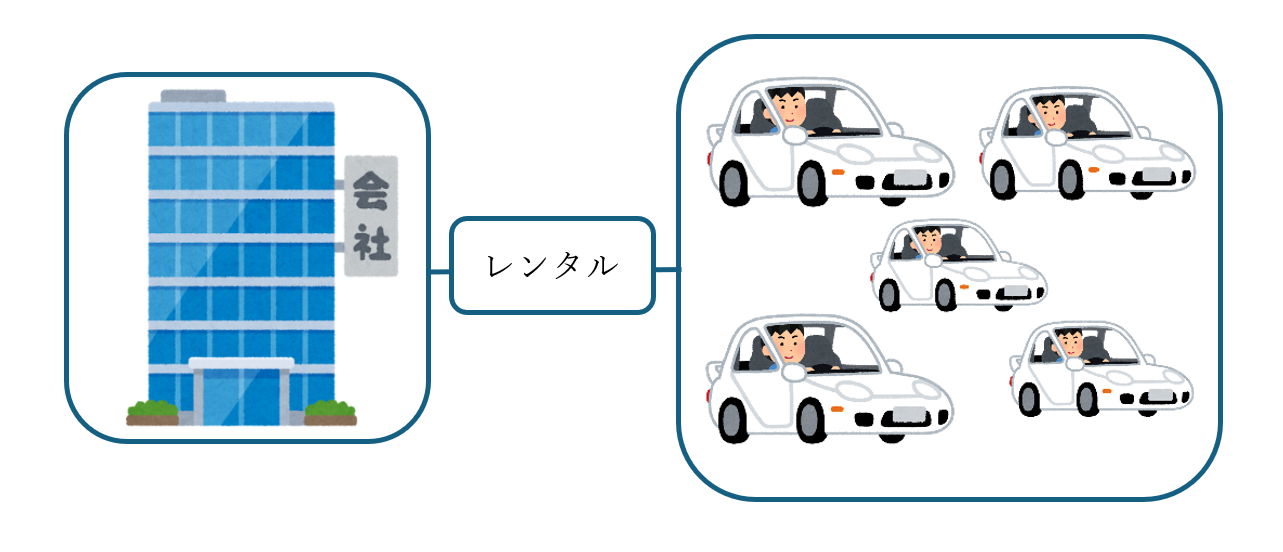
社有車について
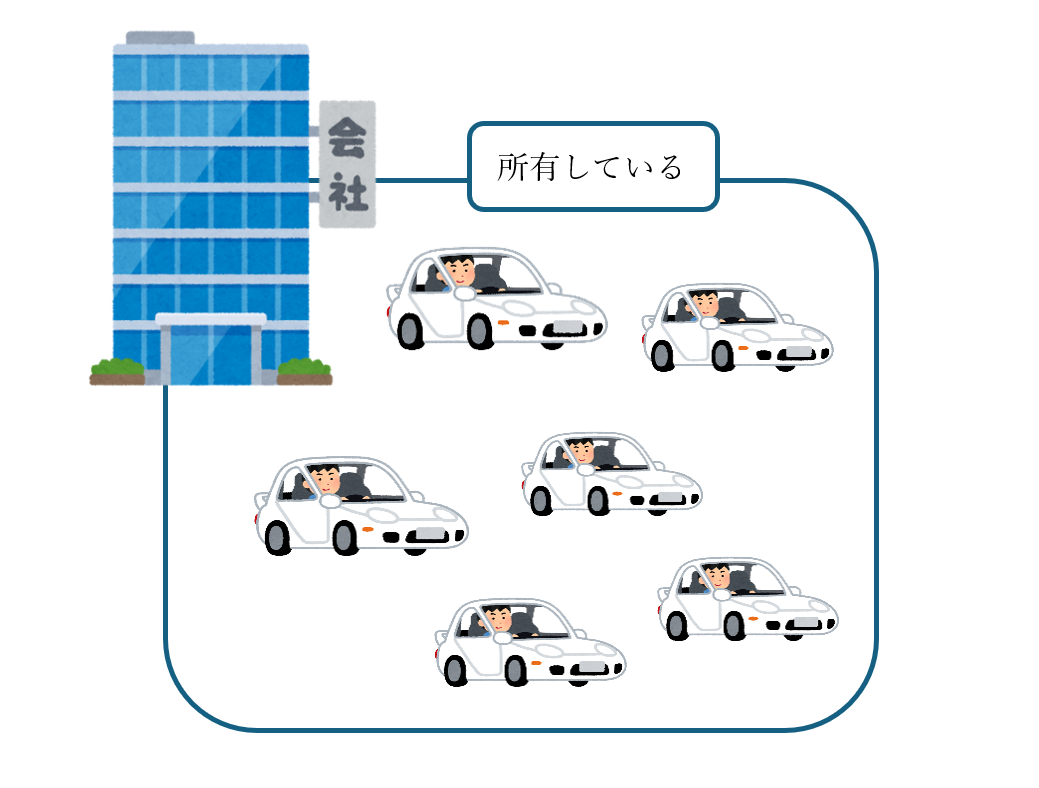
社用車を導入するメリット
企業イメージの向上
ロゴ入りの社用車や、清潔で安全な車両を使うことは、企業の信頼性を高めます。特に顧客訪問が多い業種では、第一印象を左右する重要なポイントです。
業務効率の改善
営業担当者が公共交通機関に頼らず、効率的に移動できることで、訪問件数の増加や業務スピードの向上につながります。また、配送や出張でも時間のロスを減らせます。
福利厚生としての価値
社員が社用車を使えることで、私用車を業務に使う負担が減ります。ガソリン代や保険の心配がなくなるため、社員満足度の向上にも寄与します。
社用車を導入するデメリットとリスク
維持費や管理コストの負担
社用車は購入費用だけでなく、保険、税金、車検、メンテナンスなどの維持費がかかります。リースの場合も月額料金が固定で発生するため、計画的な資金管理が必要です。
交通事故や法的リスク
万が一の事故発生時、会社の社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。社員が業務中に起こした事故は「使用者責任」として会社が賠償を求められる場合もあります。
社員の利用ルールの徹底課題
私的利用をどう制限するか、ガソリンカードやETCカードの不正使用を防ぐにはどうするか、ルールを明確にしなければなりません。管理体制の不備は不正利用の温床となります。
社用車の種類と活用シーン
営業用車両:顧客訪問や新規営業に使用
社員送迎・役員車:役員や来客の送迎に利用
配送・業務支援車両:商品配送や工事現場での利用
業種や業務内容に応じて、必要な車種や台数を検討することが大切です。

社用車の導入方法:購入かリースか?
購入する場合の特徴
資産として計上される
減価償却の対象になる
長期的に利用するなら割安
リース・カーシェアの活用方法
初期費用を抑えられる
車検や保険がリース料に含まれるケースが多い
必要な期間だけ利用可能
税制・会計上の取り扱い比較
購入:固定資産として計上、減価償却が必要
→減価償却のルール
社有車として購入した場合、車両は固定資産として計上され、耐用年数に応じて減価償却を行います。普通車の耐用年数は6年が一般的です。
リース:リース料を損金として処理可能
→リース料の損金計上
リース契約の場合は、毎月のリース料を損金として計上できます。資産計上や減価償却の必要がなく、経理処理がシンプルです。
企業のキャッシュフローや税務戦略に応じて選ぶことがポイントです。
社用車の管理方法と注意点
社内ルールの策定
業務目的外の利用禁止
飲酒運転の厳禁
点検・清掃の義務化
事故発生時の報告フロー
ガソリンカード・ETC管理
これらを就業規則や社内マニュアルに盛り込み、社員全員に周知徹底しましょう。
社用車選びのポイント
車種・サイズの選定基準
業務内容に応じた選定が重要です。
都市部営業 → コンパクトカー
荷物配送 → バンやワゴン車
無駄に大きな車を選ぶと維持費が高騰するため、使用目的を明確にしましょう。
燃費・環境性能を考慮する
燃費性能やハイブリッド・EVなどの環境対応車は、長期的にコスト削減につながります。また、環境への配慮はCSR(企業の社会的責任)の観点からもプラスになります。
安全面(安全装備・自動運転支援)
最新車両には、自動ブレーキ、車線逸脱防止システム、ドライブレコーダーなどの安全装備が搭載されています。事故リスクを低減するため、導入時には安全性能を重視しましょう。
社用車利用に関する法令とコンプライアンス
道路交通法の遵守
当然ながら交通ルールを守ることは必須です。特に長時間運転や過労運転は事故リスクを高めるため、労働時間管理とセットで考える必要があります。
労働安全衛生の観点
ドライバーの健康状態を把握し、安全に運転できる環境を整えることは企業の義務です。アルコールチェックや運転前点呼を取り入れる企業も増えています。
個人情報保護の留意点
社用車にカーナビやテレマティクス機器を搭載する場合、運転履歴や位置情報が記録されます。これらの情報は個人情報に該当するため、適切な管理が求められます。
社用車導入を検討する企業へのアドバイス
導入前に明確化すべき目的
営業効率を高めたいのか
福利厚生を充実させたいのか
配送や業務支援を効率化したいのか
目的によって必要な車種や台数は大きく異なります。
費用対効果のシミュレーション
購入とリースのコスト比較、維持費の試算、事故リスクを含めた保険料の検討を行い、長期的な費用対効果をシミュレーションしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 社用車と社有車の違いは何ですか?
A1. 社用車は業務に利用する車全般を指し、リースやレンタルも含みます。一方、社有車は企業が購入し所有する車のことです。
Q2. 社用車を私的に利用してもいいですか?
A2. 原則として業務利用が前提です。私用利用は会社の規定によりますが、課税や保険の問題が生じる可能性があります。
Q3. リースと購入、どちらがおすすめですか?
A3. 短期間・初期費用を抑えたい場合はリース、長期利用で総コストを下げたい場合は購入が適しています。
Q4. 社用車導入に必要な保険は?
A4. 自賠責保険に加え、対人・対物補償のある任意保険に加入することが必須です。
Q5. 社用車にドライブレコーダーは必要ですか?
A5. 必須ではありませんが、事故時の証拠保全や社員教育に役立つため、導入する企業が増えています。
Q6. 社用車の経費処理はどうすればいいですか?
A6. 購入なら減価償却、リースならリース料を損金計上します。私用利用部分は給与課税となる場合があるため注意が必要です。
まとめ
社用車とは、企業が業務で利用する車全般を指し、リースやレンタルも含まれます。一方で社有車は購入して所有する車を意味します。この違いを理解したうえで、目的に合った導入方法を選ぶことが重要です。
メリットとしては業務効率や企業イメージ向上があり、デメリットとしては維持費や事故リスクが挙げられます。近年はEV導入やカーシェア活用など新しい選択肢も増えており、企業の状況に応じた柔軟な導入が求められます。
適切なルール策定と社員教育を行えば、社用車は企業の成長を支える大きな力となるでしょう。
しかし、社用車の管理は煩雑なものです。社用車の管理をするシステムをご検討の場合は、ODIN 動態管理の「車両管理」機能をご覧ください。
ODIN(オーディーン) 動態管理について
詳しく知りたい、まずは試してみたいなどお気軽にお問い合わせください。
 この記事を読むとわかること
この記事を読むとわかること